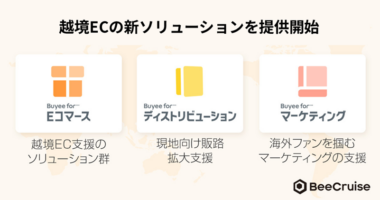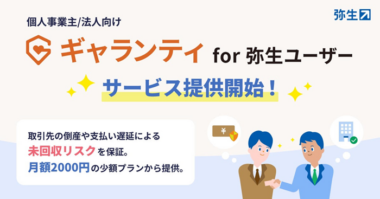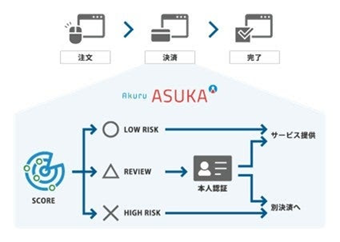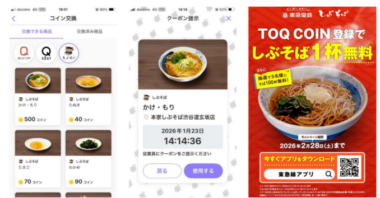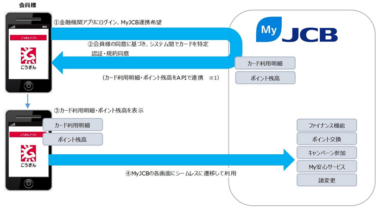2025年8月25日15:17
GMO AI&ロボティクス商事(以下、GMO AIR)は、2025年8月25日~31日(各日11:00~13:00、15:00~17:00)まで、日本科学未来館(東京都江東区)でAI 対話型ロボットの実証実験を実施している。

AI 対話型ロボットの実証では、ロボットが展示エリア内を自律移動しながら、来館者に多言語での展示解説や案内を行う。AIロボットは、GMO AIRが開発したもので、対話内容から動作プログラムに至るまで、ロボットアプリケーションの約 80%は AI が自動生成しているという。同プログラムによる対話型ロボットの実証は、国内初の取り組みだ(GMO AIR 調べ)。
今回の実証実験では、5階の常設展示「プラネタリー・クライシス-これからもこの地球でくらすために」をロボットが移動し、展示の解説をしたり、展示に関する質問に回答する。言語は日本語・英語・中国語・韓国語の4カ国語に対応する。
GMOインターネットグループ グループ専務執行役員 GMO AIR代表取締役社長 内田朋宏氏は「老若何女の方々にAIを活用してもらい、想像力を膨らませていただきたい」と述べる。AI対話型ロボットは、来館者への案内だけではなくコミュニケーションを図ることができるのが特徴だ。
同AIロボットは、Microsoft AzureのOpen AIを活用している。また、外部知識から回答を検索して生成する「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」技術を搭載。展示解説に加え、科学に関する質問にも回答可能だ。例えば、地球温暖化の説明などもインタラクティブに可能だという。なお、事実とは異なる情報や存在しない情報を生成する「ハルシネーション」に関しては、基本的に与えた情報を基に応えるためきわめて可能性が低いという。

GMO AIR 金明源氏によると、今回の実証の目的は大きく2つ。1つ目はAIとロボティクスを活用することで、コミュニケーション手段の実用化の可能性を探ることだ。2つ目は、来館者がAIロボットを体験することで、未来を感じてもらい、顧客体験価値が高まるかを検証する。
日本科学未来館には年間100万人の来館者が訪れる。未来館では、展示やイベントにとどまらず、同館で行われる最先端の研究開発や実証実験などに一般の人々が参加する「未来をつくるラボ」としての活動に取り組んでいる。今回のGMO AIRとの連携もその一環だ。中でもAIやロボティクスに着目しているという。日本科学未来館 樋口 貢介氏は「AIはスマホで十分な対応ができますが、ロボティクスをかぶせることでリアルで会話を行えます。今後、実証実験を通じてさまざまな展開を企画しています」と話す。

このコンテンツは会員限定となっております。すでにユーザー登録をされている方はログインをしてください。
会員登録(無料)をご希望の方は無料会員登録ページからご登録をお願いします。