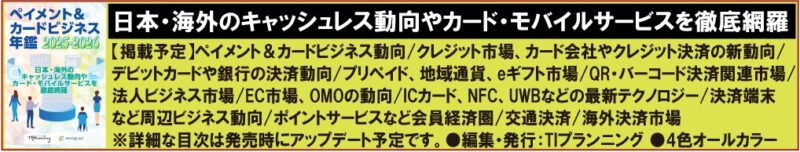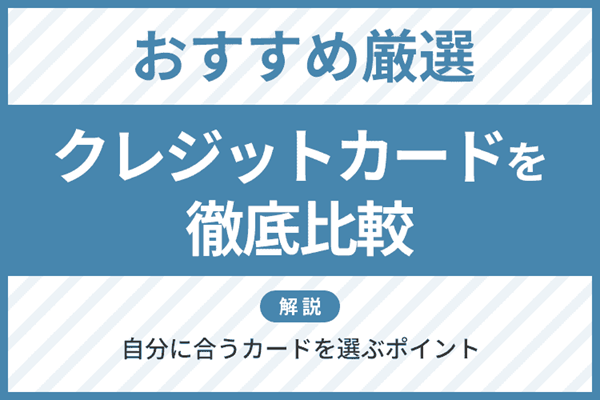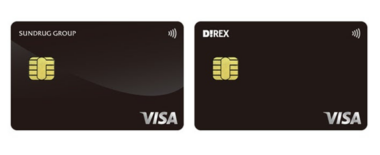2020年4月24日8:00
国内において、長きにわたりマーケティングやCRM関連の情報を配信してきたアイ・エム・プレス 代表取締役/「インタラクティブ・マーケティングまとめサイト」編集長 西村道子氏にデータ・ドリブン・マーケティングについて紹介してもらった。西村氏は、マーケティング・リサーチ会社勤務時代から約40年間にわたりダイレクトマーケティングの調査・研究に従事。1995年から足掛け20年間にわたり、この分野の専門誌を発行してきたが、2015年には「インタラクティブ・マーケティングまとめサイト」を立ち上げ、同誌掲載事例の無償公開を開始。現在は、コンサルティングを手掛ける傍ら、マーケティング、顧客接点、異文化コミュニケーションなどをテーマに執筆活動を展開している。
株式会社アイ・エム・プレス 代表取締役/
「インタラクティブ・マーケティングまとめサイト」編集長 西村道子
はじめに
マーケティングの世界では、新しいカタカナ言葉が流行ったかと思えば、いつしか忘れ去られていくことが少なくない。そんな中でもここ数年、赤丸急上昇中の言葉に「データ・ドリブン・マーケティング」がある。コトバンクによると、データ・ドリブン・マーケティングとは「販売実績や顧客情報などのデータを総合的に分析し、意志決定や企画立案に役立てるマーケティング手法」を意味しており、1980年代後半から1990年代にかけて多用されたデータベース・マーケティング※1とほぼ同義である。
データ・ドリブン・マーケティングに類似したカタカナ言葉としては、ほかにもダイレクトマーケティング※2やOne to Oneマーケティング※3、CRM(Customer Relationship Management)※4などがある。各々の概念には重複する部分も大きいが、“ビッグデータの時代”と言われる中、データ・ドリブン・マーケティングで取り扱われるデータの種類や量は、かつてとは比較にならないほどに増大している。
私は前職のマーケティング・リサーチ会社勤務の時代から約40年間にわたり、今で言うところのデータ・ドリブン・マーケティングに関するメディアやコンテンツの企画・制作に携わってきた。現在は、1995~2014年に発行していたこの分野にかかわる専門誌、月刊『アイ・エム・プレス』掲載の企業事例を「インタラクティブ・マーケティングまとめサイト」に公開する一方、関連領域のコンサルティングや執筆活動を行っている。
そこで本稿では、店舗小売業におけるデータ・ドリブン・マーケティングの歩みを、「インタラクティブ・マーケティングまとめサイト」上に公開された企業事例を交えて振り返ってみたい。なお、一口に店舗小売業におけるデータ・ドリブン・マーケティングと言ってもさまざまな取り組みがあるが、ここではあくまでも顧客データに基づくマーケティング活動にフォーカスしている。

店頭商品の宅配・通信販売への取り組み
店舗小売業におけるデータ・ドリブン・マーケティングの1つ目のパターンとして取り上げるのは、店頭商品の宅配・通信販売である。
古くは米穀店や酒販店、牛乳販売店のご用聞きがこれに該当するが、大手企業によるこうした取り組みが本格化したのは、インターネットが一般家庭に広く普及し始めてからのこと。2000年にユニクロと良品計画がECに参入したのを機に、SPA※5による取り組みが活発化したかと思えば、2006~2007年には大手・中堅スーパーによるネットスーパーへの参入が相次いだ。
月刊『アイ・エム・プレス』では、2008年2月号で「急速に広まるネットスーパー/ネット宅配の魅力」を特集した。これによると、イトーヨーカ堂が2001年からネットスーパーの実験に着手し、2007年から本格展開を開始。首都圏で食品スーパーを手がけるサミットでは、2007年4月にネットスーパーに参入。後に、既存の店舗とは別立ての配送網を構築したことで注目されたが、2014年にはあえなくこの分野から撤退。現在、大手スーパーの中では、イトーヨーカ堂のほか、イオン(イオンリテール)、西友(現在は楽天西友ネットスーパーマーケティング)などがネットスーパーを展開している。
特集当時のイトーヨーカ堂への取材によると、ネットスーパーの会員数は約15万人(2007年12月現在)。「週末は店舗で、平日はネットスーパーで」などと、2つのチャネルを使い分けている会員がほとんどであった点や、レシピ機能など会員顧客の購買意欲を促進する仕掛けを競合に先駆けて導入していた点が注目された。ちなみに2019年9月時点の会員数は150万人に達しており、今なお2つのチャネルを併用する会員が多いそうだ。
また月刊『アイ・エム・プレス』2008年5月号では、マルチチャネル展開に乗り出すSPA(Speciality store retailer of Private label Apparel)が増加していることを受けて「SPA企業のマルチチャネル戦略」を特集。当時の「THE SUIT COMPANY」(青山商事)への取材によると、同店では2002年からECに参入、2008年時点では店舗と同じラインナップをECサイトでも紹介し、ほぼ1店舗分の売り上げを計上。顧客層についても、ECでの購入顧客の80%前後は店舗での購入経験があり、チャネルによる購買傾向の違いはほとんどないとのことだった。
このほか高島屋や三越、大丸などの大手百貨店では、明治時代から通信販売を展開。その後、1970年代~1980年代半ばにかけては、中堅の百貨店やスーパーが続々とこの分野に参入した。しかし、当時、通信販売を展開していた多くの百貨店・スーパーでは、店舗とは異なる商品を、異なるターゲットに販売していたことから、既存の店舗とは別の事業として通信販売を展開していたと言えるだろう。
組織化された顧客への情報提供
店舗小売業におけるデータ・ドリブン・マーケティングの2つ目のパターンは、組織化された顧客への情報提供である。
店舗小売業において古くから展開されていた顧客の組織化手法としては、多くの百貨店が運営してきた商品代金の全部または一部を前払いする仕組みの会員制度(1972年に前払式特定取引として割賦販売法の対象となる)と、得意客に購入代金の割引や、購入回数・金額に応じたプレゼントの進呈、イベントの開催、会報の送付などを行う顧客サービスとしての会員制度が挙げられる。
その後、1970年代半ばになると、百貨店など大手店舗小売業が自社ブランドのクレジットカードを発行、会員に割引などの特典を提供するようになった。しかし、カード会社との提携によりこれを実現している企業においては、取扱手数料に加えて会員に割引を提供したのでは経営が圧迫されかねない。そこで1990年代後半にはポイントカードの発行が活発化。これにより現金払いを含むトータルな購買履歴が捕捉できるようになると共に、CRMのインフラが整備されることになった。
月刊『アイ・エム・プレス』2006年4月号では、「進化するポイントシステム」を特集。ポイントカード発行企業の増加に伴い、ポイント自体による差別化が困難になる中、これをCRMのインフラとして戦略的に活用する企業が増えてきたとして、東急百貨店の「クラブ キュウポイント」TOPカードなどの事例を紹介。同社では年間購入金額に応じて会員を5つのグレードに分けてポイント付与率を差別化すると同時に、各グレードに合わせた特典を提供することで、顧客の維持・再来店の促進を図っていた。
一方、2000年代に入りインターネットが人々の生活に浸透してくると、組織化された顧客への情報提供方法はオフラインからオンラインへとシフトしてきた。インターネットが浸透する以前には、紙ベースのカタログや会報を送付したり、イベントやキャンペーンをフックにダイレクト・メールで来店促進を図ったりしていたものが、eメール、Webサイト、さらにはスマホ・アプリなどへと広がっていったのだ。
また、店舗小売業のデータ・ドリブン・マーケティングにおいて大きな役割を担ってきたのがケータイである。ケータイはいつでも、どこでも利用できるパーソナルなデバイスであり、その機能も音声通話に限らず、インターネットへの接続や「おサイフケータイ」などに広がっている。そこで、インターネットに接続できる端末が普及した2000年代半ば頃からは、ケータイをマーケティングに活用する企業が増加。さらに2010年代にはスマートフォンの普及を受けて、スマホ・アプリの活用が活発化してきた。
月刊『アイ・エム・プレス』2012年11月号では、「顧客に寄り添うスマホ・アプリ活用術」を特集。この中で取り上げたセレクトショップのユナイテッドアローズでは、2012年8月より、ポイントプログラムの会員証機能を持つスマホ・アプリの提供を開始。会員が配信情報のカテゴリーを選べるようにする、会員の基本属性や購買履歴に基づき最適なクーポンを配信するなど、限界が見えてきたメルマガに代わる新たな情報提供手段としてのスマホ・アプリの可能性を見据えて、さまざまな取り組みを展開していた。
オフラインとオンラインの融合
以上、店舗小売業におけるデータ・ドリブン・マーケティングとして、店頭商品の宅配・通信販売と、組織化された顧客への情報提供を紹介したが、2000年代に入り、インターネットが広く人々の生活に浸透してくると、これらのプロセスで用いられるメディア/チャネルはオフラインからオンラインへとシフトしていった。とは言え、すべてをオンラインに移行するというのではなく、オフラインとオンラインの効果的な融合方法が模索されるようになったと言えるだろう。
例えば、月刊『アイ・エム・プレス』2013年5月号では、「CRMサイクル構築に向けて 進化するO2O戦略」を特集。O2O ※6はOnline to Offlineを略した言葉で、店頭集客の主力メディアとしての役割を担ってきた新聞折り込みチラシのリーチ率の低下や、ショールーミング※7の台頭などの打開策として注目を浴びた概念。この特集では、店頭で実施するキャンペーンを「Yahoo! JAPAN」で広く告知し、ネット経由での応募者に全国の店舗で使えるクーポンを進呈して来店促進に繋げたダイエーなどの事例を取材した。
また販売チャネルの融合については、2000年代には店舗小売業がECに、あるいは通信販売会社が店舗販売に進出したりすることを意味するマルチチャネル※8という言葉が用いられていたが、今日ではこれに代わってオムニチャネル※9という言葉が一般化している。オムニチャネルとは、オフラインかオンラインかを問わず、すべてのチャネルで顧客とコミュニケーションを行うこと。マルチチャネルが、ともするとチャネル間のコンフリクトを起こしかねない側面を持っていたのに対し、あくまでも顧客目線に立つという点が大きな違いである。
月刊『アイ・エム・プレス』2013年9月号では、「小売業に革新をもたらす!! 顧客起点のオムニチャネル戦略」を特集。この時のリーディング・カンパニーへの取材によると、大手百貨店の高島屋が「今後5年間で、原則的にリアル店舗で取り扱う全商品をECサイトでも販売する体制を整える」と息巻けば、大手セレクトショップのビームスでは、店舗とECのポイント共通化などにより「顧客が店舗とECをシームレスに利用できる環境を整備する」とそのビジョンを語っていた。
先に述べた通り、かつて百貨店の通信販売においては、店舗とは異なる商品を、異なるターゲットに販売していた。伊勢丹などごく一部の百貨店では、通信販売でも店舗と同一の商品を取り扱うというチャレンジを行っていた時期もあるが、店舗販売と通信販売の経営構造の違いもあり、これが陽の目を見ることはなかったと記憶している。そしてそれから数十年が経過した今日、情報テクノロジーの進化に支えられてオムニチャネル化が進展。顧客への価値提供に向けて、店舗とECがそれぞれの特性を生かしながらも、スクラムを組み始めた感がある。
店頭における情報収集機能の強化
最近のもう1つのトレンドと言えるのが、店頭における情報収集機能の強化である。ポイントカードにより店頭における購買履歴がトータルで把握できるようになったことはすでに述べたが、ここにきて注目されているのは、店頭での顧客の行動を可視化する取り組み。店頭に設置したカメラによる来店客の行動観察は以前から行われていたが、昨今ではテクノロジーが進展し、ロボット接客や「Amazon Go」に代表される無人店舗が現実のものとなる中、こうした取り組みはますます精緻化していると言えるだろう。
例えば2019年11月にリニューアル・オープンした渋谷パルコでは、デジタルサイネージとスマホ・アプリを活用して店頭とECをシームレスに繋ぐオムニチャネル型のショッピング体験を提供する傍ら、店頭のカメラや店内の案内を行う情報端末のログを通して来店客の情報を収集、同社やテナントのマーケティング活動にフィードバックしている。店頭での顧客の行動を可視化するこうした取り組みは、購入、あるいは非購入に至った理由を推し量り、売り場のレイアウトや棚割、POPのあり方などを改善、カスタマー・エクスペリエンス(CX) ※10を向上する上で、大きなヒントをもたらしてくれると言えるだろう。
さらに最近、注目されているのは、店頭を新商品にかかわる情報収集拠点として活用しようという動きだ。前出の渋谷パルコにクラウド・ファンディングのCAMPFIREが出店、店頭に展示した試作品などへの来店客の反応をカメラや人手により収集し、リポートするサービスを開始したほか、2020年夏にはこの分野の大手である米b8ta(ベータ)の国内1号店が新宿マルイ本館にオープンするという。つまり、店頭で収集した来店客の情報が、店舗小売業におけるCX向上のみならず、スタートアップ企業の意志決定や、メーカーのテスト・マーケティングのためにも活用されるようになってきたのだ。
オムニチャネル化により店舗とECの境目がなくなるかと思えば、店舗の情報収集機能が再認識され、メーカー・卸・小売・エンドユーザーというサプライチェーンを超える情報のやりとりが活発化する。店舗小売業におけるデータ・ドリブン・マーケティングとは、換言すれば店舗小売業におけるデジタル・トランスフォーメーションであり、それまでの“勘と経験と度胸”に基づくビジネスを、データに基づく科学的なビジネスへと昇華させていく仕組みなのかもしれない。
※各ページに記した本稿で使用した用語の解説は、月刊『アイ・エム・プレス』(アイ・エム・プレス)、『データベース・マーケティング用語辞典』(ジェリコ・コンサルティング)、『ONE to ONEマーケティング』(D.ペパーズ+M.ロジャーズ著、ダイヤモンド社)、ウィキペディアなどの記述を筆者が簡略化、あるいは加筆したものです。
※本文中で紹介した、月刊『アイ・エム・プレス』に掲載した企業事例の全文が、「インタラクティブ・マーケティングまとめサイト」上で無料でご覧いただけます。
https://im-press.jp/index.php
※1 データベース・マーケティング:顧客データベースに基づくマーケティング。
※2 ダイレクトマーケティング:1つまたは複数の広告メディアを活用した、双方向で効果が測定できるマーケティング。
※3 One to Oneマーケティング:1人1人の顧客を把握し、彼らと1対1で対話を続け、個別の仕様に従ってカスタマイズした製品・サービスを提供すること。
※4 CRM(Customer Relationship Management):顧客満足度と顧客ロイヤルティの向上を通して、売り上げの増大と収益の向上を目指す経営戦略・手法。
顧客関係性管理などと訳される。
※5 SPA(Speciality store retailer of Private label Apparel):製造と小売りを自らがコントロール・実施しているアパレル企業。製造小売業と訳される。
※6 O2O(Online to Offline):eメールやWebサイトなどオンライン・メディアを活用して、店舗などオフライン上での行動を促進する施策。
例えば飲食店などがWebサイトを通してクーポンを配布し、来店を促すなどの例がある。
※7 ショールーミング:小売店店頭で確認した商品をその場では買わず、ECにより店頭より安い価格で購入すること。
※8 マルチチャネル:顧客に対して店舗、ECサイト、カタログなど複数のチャネルを用意すること。
※9 オムニチャネル:「すべての」を意味する英語の接頭詞である“Omni”と、「経路」を意味する英語の“Channel”を組み合わせた造語。小売業のオムニチャネル戦略とは、
オフライン(店舗など)かオンラインかを問わず、すべてのチャネルで顧客とコミュニケーションを図ろうとする戦略。
※10 カスタマー・エクスペリエンス:さまざまな顧客接点において、顧客が企業から受ける経験や感覚がもたらす価値。顧客経験価値などと訳される。
カード決済&リテールサービスの強化書2020より